『兵庫県神道青年会』とは、兵庫県内の40才未満の青年神職によって構成されております。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
『戦没学徒の慰霊と顕彰』
【趣旨】
昭和十八年戦局愈々重大の秋、十月二十一日午前八時秋雨降りしきる明治神宮外苑陸上競技場にて「出陣学徒壮行会」が挙行された。参列した出陣学徒は全国を代表し東京帝大以下東京・神奈川・千葉・埼玉県下の七十七校より、出陣する学徒約七万名は、銃を執り剣を帯び脚絆を巻き、神宮外苑の落葉を踏みしめそれぞれの位置に結集、送る学徒百七校六万五千名が会場を埋め尽くした。時の東条英機内閣総理大臣が「願はくば、青年学徒諸君、私は諸君が昭和の御代に於ける青年学徒の不抜なる意気と必勝の信念とを以って護國の重責を全うし、後世に永く日本の光輝ある伝統を残されんことを諸君に期待し、且つこれを確信するものである。」との訓辞の後に、出陣学徒を代表して東大・江橋慎四郎が「生等今や見敵必殺の銃剣を提げ積年忍苦の精神研鑽を挙げて悉く此の光栄ある重任に捧げ、挺身以て頑敵を撃滅せん、生等もとより生還を期せず」と悲壮な決意を誓ふと会場には「海ゆかば」「嗚呼紅の血は燃ゆる」の大合唱が湧き起こった。かくして彼等はペンを剣に持ち替へ戦場に赴ひて行ったのである。終戦迄に入隊した学徒は、その数約三十万人にも上ると言ふ。本年で六十五回目の秋を迎へる事になる。
然るに、戦後、戦没学徒に対する慰霊と顕彰は進んでゐない。全国で学徒兵として出征した総数も政府による公式な数字が発表されてをらず、学問的にも資料が戦災や戦後の学制改革により失はれたものが多く未だに詳細な研究も為されてゐない。死者数に関しては概数すら示す事が出来ないのが現状である。
昭和四十二年、兵庫県南あわじ市の福良港を見下ろす大見山の高台に、志半ばにして国難に殉じた学徒の御霊を慰め、併せて生き残った動員学徒との交流の場として建設された我が国唯一の施設である戦没学徒記念「若人の広場」は、昭和四十七年、当時皇太子同妃両殿下で在らせられた天皇皇后両陛下の御台臨を仰ぎ、「この広場を訪れる今日の若者が、ここに刻まれた歴史の事実とその重みを深く考へ、ここに燃へ続ける『ともしび』の理念を心に刻み、平和への願ひを絶やさず明日に向かって生きて行くことが、戦没した学徒へのせめてもの慰霊でありませう」との御言葉を賜った。しかし、陛下の御言葉も虚しく、「若人よ天と地をつなぐ灯たれ」と永遠の炎を燃やし続けることを約束してゐたはずの『ともしび』は、その炎も消へて久しい。阪神淡路大震災を機に完全に閉鎖され、今では施設全体が荒廃し、放置された儘なのである。
これが我が国の慰霊なのか。否、決して違ふ筈である。今こそ我々青年神職が、今再び戦没学徒の愛国の衷情に想ひを馳せ、学徒出陣とは何であったのかを学び、我が国の戦没学徒への慰霊の現状を肌で感じると共に、慰霊の誠を捧げる秋なのである。それを為し得てこそはじめて、その大いなる遺徳を広め伝へる顕彰へと進めるのではなかろうか。
全国会員諸兄よ、戦没学徒は泣いてゐる。
【主催】
神道青年全国協議会
神道青年全国協議会ホームページへのリンク
【主管】
神道青年全国協議会渉外委員会
【期日】
平成20年10月20日(月曜)~21日(火曜)
【対象】
神道青年全国協議会会員
【申込】
各単位会毎のご案内取り纏めとなります。
宜しくお願い申し上げます。
【事業概要】
≪第1日目≫講義
第一講「学徒出陣に関して」
講師 上杉千郷先生
皇學館大学 理事長
鎮西大社諏訪神社 名誉宮司
第二講「英霊の慰霊と顕彰について」
講師 青山繁晴先生
㈱独立総合研究所 代表取締役社長
兼 首席研究員
終了後 レポート作成
~会場 生田神社会館~
兵庫県神戸市中央区下山手通1-2-1
(078)391-8765
≪第2日目≫
正式参拝~伊弉諾神宮
講話 講師 本名孝至先生
伊弉諾神宮 宮司
全國戦没学徒追悼祭
参列 全國戦没学徒追悼祭
見学 戦没学徒記念『若人の広場』
終了後 現地にて閉講式、解散
(但し、神戸方面にはバス送迎)
兵庫県神道青年会ホームページへのリンク
【趣旨】
昭和十八年戦局愈々重大の秋、十月二十一日午前八時秋雨降りしきる明治神宮外苑陸上競技場にて「出陣学徒壮行会」が挙行された。参列した出陣学徒は全国を代表し東京帝大以下東京・神奈川・千葉・埼玉県下の七十七校より、出陣する学徒約七万名は、銃を執り剣を帯び脚絆を巻き、神宮外苑の落葉を踏みしめそれぞれの位置に結集、送る学徒百七校六万五千名が会場を埋め尽くした。時の東条英機内閣総理大臣が「願はくば、青年学徒諸君、私は諸君が昭和の御代に於ける青年学徒の不抜なる意気と必勝の信念とを以って護國の重責を全うし、後世に永く日本の光輝ある伝統を残されんことを諸君に期待し、且つこれを確信するものである。」との訓辞の後に、出陣学徒を代表して東大・江橋慎四郎が「生等今や見敵必殺の銃剣を提げ積年忍苦の精神研鑽を挙げて悉く此の光栄ある重任に捧げ、挺身以て頑敵を撃滅せん、生等もとより生還を期せず」と悲壮な決意を誓ふと会場には「海ゆかば」「嗚呼紅の血は燃ゆる」の大合唱が湧き起こった。かくして彼等はペンを剣に持ち替へ戦場に赴ひて行ったのである。終戦迄に入隊した学徒は、その数約三十万人にも上ると言ふ。本年で六十五回目の秋を迎へる事になる。
然るに、戦後、戦没学徒に対する慰霊と顕彰は進んでゐない。全国で学徒兵として出征した総数も政府による公式な数字が発表されてをらず、学問的にも資料が戦災や戦後の学制改革により失はれたものが多く未だに詳細な研究も為されてゐない。死者数に関しては概数すら示す事が出来ないのが現状である。
昭和四十二年、兵庫県南あわじ市の福良港を見下ろす大見山の高台に、志半ばにして国難に殉じた学徒の御霊を慰め、併せて生き残った動員学徒との交流の場として建設された我が国唯一の施設である戦没学徒記念「若人の広場」は、昭和四十七年、当時皇太子同妃両殿下で在らせられた天皇皇后両陛下の御台臨を仰ぎ、「この広場を訪れる今日の若者が、ここに刻まれた歴史の事実とその重みを深く考へ、ここに燃へ続ける『ともしび』の理念を心に刻み、平和への願ひを絶やさず明日に向かって生きて行くことが、戦没した学徒へのせめてもの慰霊でありませう」との御言葉を賜った。しかし、陛下の御言葉も虚しく、「若人よ天と地をつなぐ灯たれ」と永遠の炎を燃やし続けることを約束してゐたはずの『ともしび』は、その炎も消へて久しい。阪神淡路大震災を機に完全に閉鎖され、今では施設全体が荒廃し、放置された儘なのである。
これが我が国の慰霊なのか。否、決して違ふ筈である。今こそ我々青年神職が、今再び戦没学徒の愛国の衷情に想ひを馳せ、学徒出陣とは何であったのかを学び、我が国の戦没学徒への慰霊の現状を肌で感じると共に、慰霊の誠を捧げる秋なのである。それを為し得てこそはじめて、その大いなる遺徳を広め伝へる顕彰へと進めるのではなかろうか。
全国会員諸兄よ、戦没学徒は泣いてゐる。
【主催】
神道青年全国協議会
神道青年全国協議会ホームページへのリンク
【主管】
神道青年全国協議会渉外委員会
【期日】
平成20年10月20日(月曜)~21日(火曜)
【対象】
神道青年全国協議会会員
【申込】
各単位会毎のご案内取り纏めとなります。
宜しくお願い申し上げます。
【事業概要】
≪第1日目≫講義
第一講「学徒出陣に関して」
講師 上杉千郷先生
皇學館大学 理事長
鎮西大社諏訪神社 名誉宮司
第二講「英霊の慰霊と顕彰について」
講師 青山繁晴先生
㈱独立総合研究所 代表取締役社長
兼 首席研究員
終了後 レポート作成
~会場 生田神社会館~
兵庫県神戸市中央区下山手通1-2-1
(078)391-8765
≪第2日目≫
正式参拝~伊弉諾神宮
講話 講師 本名孝至先生
伊弉諾神宮 宮司
全國戦没学徒追悼祭
参列 全國戦没学徒追悼祭
見学 戦没学徒記念『若人の広場』
終了後 現地にて閉講式、解散
(但し、神戸方面にはバス送迎)
兵庫県神道青年会ホームページへのリンク
PR
天皇が、歴代の天皇をはじめとする主たる皇族の霊を奉祀する『皇霊祭』は、春分の日『春季皇霊祭』と秋分の日『秋季皇霊祭』の年二回です。
昭和22年(1947)までの『秋季皇霊祭』という祭日は、昭和23年(1948)公布施行の祝日法(国民の祝日に関する法律)により、「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」ことを趣旨とする『秋分の日』(国民の祝日)として制定されました。
また「祝日法」の施行に伴い、大正元年(1912)より施行されていた勅令「休日ニ関スル件」が廃止となりました。
『秋分の日』は毎年9月23日ごろですが、具体的には国立天文台が作成する『暦象年表』に基づき閣議で決定されています。
昭和22年(1947)までの『秋季皇霊祭』という祭日は、昭和23年(1948)公布施行の祝日法(国民の祝日に関する法律)により、「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」ことを趣旨とする『秋分の日』(国民の祝日)として制定されました。
また「祝日法」の施行に伴い、大正元年(1912)より施行されていた勅令「休日ニ関スル件」が廃止となりました。
『秋分の日』は毎年9月23日ごろですが、具体的には国立天文台が作成する『暦象年表』に基づき閣議で決定されています。
兵庫県神道青年会 神戸市支部主催
日本文化に触れる『落語の夕べ』
日時:平成20年10月25日(土曜)午後6時開演
場所:北野天満神社拝殿(神戸市中央区北野町3-12-1)
北野天満神社ホームページはここをクリック
地図は下の画像をクリックしてね





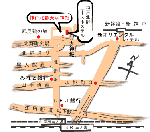
出演:桂わかば 桂とま都(桂ざこば一門)
桂ざこばの公式ホームページはここをクリック
内容:高座二席(約一時間)
対象:どなたでも参加頂けます
参加費:無料
下のチラシ画像をクリックしてね






日本文化に触れる『落語の夕べ』
日時:平成20年10月25日(土曜)午後6時開演
場所:北野天満神社拝殿(神戸市中央区北野町3-12-1)
北野天満神社ホームページはここをクリック

地図は下の画像をクリックしてね





出演:桂わかば 桂とま都(桂ざこば一門)
桂ざこばの公式ホームページはここをクリック

内容:高座二席(約一時間)
対象:どなたでも参加頂けます
参加費:無料
下のチラシ画像をクリックしてね





本日は国民の祝日であります『敬老の日』です。
『敬老の日』とは、長きに渡り我々社会のために貢献された高齢の方々をを敬い、更には長寿を祝う日であります。
実はこの日、兵庫県が発祥の地とされているのです。
その歴史をたどると、昭和22年(1947)兵庫県多可郡野間谷村(現在の多可町八千代区)の当時の村長並びに助役が、年寄りへの感謝・敬う心のもとに9月15日を『としよりの日』と定め、「敬老会」を開催したのが始まりとされています。昭和25年(1950)年には県下に、さらには全国へと広がりました。またその名称も、『としよりの日』⇒昭和39年(1964)『老人の日』⇒昭和41年(1966)『敬老の日』と改称され、国民の祝日となったそうです。
今日は肩タタキなんていかがでしょうか?
『敬老の日』とは、長きに渡り我々社会のために貢献された高齢の方々をを敬い、更には長寿を祝う日であります。
実はこの日、兵庫県が発祥の地とされているのです。
その歴史をたどると、昭和22年(1947)兵庫県多可郡野間谷村(現在の多可町八千代区)の当時の村長並びに助役が、年寄りへの感謝・敬う心のもとに9月15日を『としよりの日』と定め、「敬老会」を開催したのが始まりとされています。昭和25年(1950)年には県下に、さらには全国へと広がりました。またその名称も、『としよりの日』⇒昭和39年(1964)『老人の日』⇒昭和41年(1966)『敬老の日』と改称され、国民の祝日となったそうです。
今日は肩タタキなんていかがでしょうか?



